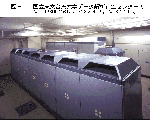 図-1 |
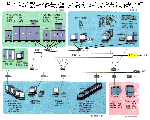 図-2 |
その後 ,1996年 1月から富士通のスーパーコンピュータVPP300/16Rとその周辺システムが導入され,本年 4月からは正式な共同利用が開始されることになった。現在の国立天文台の計算機システムの概略を紹介しておく(図-1,図-2)。
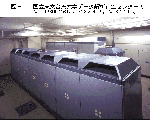 図-1 |
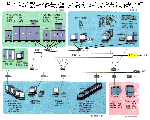 図-2 |
全体の中枢にはもちろん,スーパーコンピュータシステムVPP300/16R,VX/4R×3,VX/1Rが位置している。各PEに付帯する主記憶は 2G バイトずつなので,VX/4Rでは最大で 8G バイト,VPP300では最大 32G バイトの主記憶領域を占有した数値実験が可能である。主記憶がこれだけ広大になって来ると磁気ディスクなどの補助記憶装置も大型化を余儀なくされ,総計で 200G バイト以上の磁気ディスク装置と容量 6T バイトのVHSテープライブラリ(ASAKA製)が備えられた。
スーパーコンピュータシステム・磁気ディスク・VHSテープライブラリは一般の研究室や居室とはまったく独立した電源系と空調系に包まれた地下計算機室に納められており,ユーザは 100 Mバイト/秒 のFDDIから構成されるネットワーク経由でこれら資産の恩恵に預かることになっている。
国立天文台の以前のシステムや現在の他研究機関の大型計算機システムでは,夜間や週末になるとマシンを停止するサイトが多いようである。これは,ジョブが少ない時間帯に計算機を動かすことによる電力の浪費を避け,同時に保守時間帯を限定するという二つの目的を持っていると思われる。
それに対して我々の新しいシステムは 24時間×365日の連続運転体制を取っており,ユーザは日没や週末や年末年始といった世間一般の慣習を気にせずに自分の仕事を走らせ続けることができる。こうした連続運転は計算機を管理する側には大変な労力を要求するものであるが,利用者にしてみるといつでもどこでも思い立った時に計算を開始することができることになるので,極めてユーザ思いの運用であると言えよう。
スーパーコンピュータシステムでジョブを走らせるには,ジョブ管理用ソフトウェアNetwork Queuing System(NQS)を使用し,リモートのワークステーションからジョブをパイプキューに投入する方式を採っている。このための端末として富士通Sファミリのワークステーションが数十台用意されている。これらは主として天文台内の計算機端末室に配備され,スーパーコンピュータシステムと同様に 24時間×365日の稼働を続けており,ユーザは好きな時に立ち寄って好きなだけ仕事をこなすことができる。
これに加え,入出力装置としての高速ネットワークプリンタ(RICOH LP7200×3台),カラープリンタ(富士写真フィルムPictrography 3000×2台),8mmや DATなどの磁気テープ装置,CD-ROMドライブ,光磁気ディスクドライブなども多数整備され,考えられる限り大抵のI/O要求には応じることができると考えられる。
さて,今回我々が導入したシステムの目玉の一つにSilicon Graphics 社のハイエンドワークステーションPower ONYX(Reality Engine2)を中心とした画像処理・画像編集システムがある(図-3)。我々は,このONYXに先端可視化システムAVS(Advanced Visualization System)をはじめとするメジャーな画像処理ソフトウェアをインストールし,また,Turbo CUBEなる高機能の画像編集装置をも導入し,通常の方法では可視化が困難な科学技術計算の結果を効率良くかつ美しくプレゼンテーションするためのシステムを整えた。
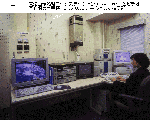 図-3 |
これら各種の機器やソフトウェアについては折りを見て専門家を招聘し,少人数演習形式の講習会を開催することによりユーザに対する教育の一環を形成している。後半で紹介する計算結果のうちのいくつかは,このPower ONYXとAVSの組み合わせで作製したものである。
数値計算を手段とする研究においては,計算そのものの信頼性はもとより,いかに見やすく理解しやすい形に計算結果を加工できるかが本質的に重要である。その意味でこれらの可視化システムはスーパーコンピュータ本体の存在価値を左右するものでさえあると言うことができる。
 |
 |
 |
 |