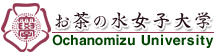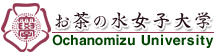| 2005年度 授業計画(シラバス) |
| |
| 科目区分・科目種 |
|
基礎講義 |
科目番号 : 05A0142 |
| 科目名 |
地学(天文気象) |
| クラス・単位数 |
|
2単位 |
|
|
| 担当教官・所属 |
自然科学研究機構
|
|
| 履修年次・学期 |
1/2/3/4 |
前期 |
|
| 曜日・時限 |
月 |
3・ 4 |
|
| 教室 |
附属図書館棟 |
101 |
|
| 受講条件・その注意 |
特に無し |
| 授業の形態 |
講義 |
| 教科書・参考文献 |
教科書は特に用いない。参考文献リストは適宜紹介して行く。 |
| 評価方法・評価割合 |
期末試験(期末筆記試験(100)) |
| 主題と目標 |
本講義のテーマは惑星の科学、とりわけ私達が住む地球と太陽系の歴史につい
てである。惑星の科学も自然科学の一分野である以上、その理解には物理や化
学の基礎的な知識、および数学に代表されるような論理思考能力が要求される。
本講義では高等学校水準の物理・化学・数学(文科系で学ぶ内容でも十分)を
基礎とし、地球および太陽系に関する最新の知見およびそれらを学ぶ上での背
景知識について概観して行く。受講生には以下のような事柄について、お茶の
水女子大学の学生として恥ずかしくない理解度へ到達できることを目標にして
頂きたい。太陽系の形成と進化と司る物理過程にはどのようなものがあり、そ
れらはどのようにして働くのか。その結果として惑星を始めとする天体がいつ
どのようにして形成し、現在どの程度までの広がりを見せているのか。また太
陽系的な惑星系が宇宙に於いて普遍的なのか特殊なのか、等々。これらの他に
も本講義では、地球の気候現象に関連するトピック(氷期・間氷期サイクルや
いわゆる地球温暖化問題)について触れる機会があるだろう。
|
| 授業計画 |
以下のような内容に関する講義を予定しているが、予定は確定ではないので
中程度の内容変更が為される可能性はある。
1. 太陽系の空間スケール (太陽系を空間尺度の基準をどのように知るか)
2. 太陽系の時間スケール (太陽系の時間尺度の基準をどのように知るか)
3. ケプラーの法則 (惑星の位置観測が太陽系天体の力学にどう関連するか)
4. 太陽系形成の物理 (ガスと塵がどうやって生命の住む惑星へ進化するか)
5. 小惑星(1) 一般論 (小惑星の発見の歴史や観測方法について概観する)
6. 小惑星(2) 小惑星の族 (天然の衝突破壊試験結果としての小惑星族の意義)
7. 小惑星(3) 地球との衝突確率 (小惑星は本当に地球に衝突する/したのか)
8. 太陽系外縁部 (太陽系のもっとも外側にある天体や彗星達の性質と運動)
9. 太陽系外惑星系 (太陽系以外にも惑星は数多い。太陽系は特殊か普遍か)
10. 氷期・間氷期サイクル (地球の氷床の拡大縮小を持たらした要因は何か)
11. 地球温暖化 "問題" (地球は本当に温暖化しているのか?その原因は何か)
講義形式は必要に応じ、黒板を使う通常の方法、スライド投射による説明、
プリント配布による解説、等を使い分ける。 |
| 学生へのメッセ−ジ |
人間が作ったわけではない地球や宇宙には、私達が
まだ答を知らない謎や疑問が無数に潜んでいます。それらの答を科学的な方法を
使って自力で探そうとする過程の中で、生きて行く上で必要となる論理的な思考
力を大いに養うことが出来る可能性があるのです。自分で考えるとはどういうこ
とか、物事を本当に「理解する」とはどういうことなのかを、地球や惑星の科学
を題材にして経験してください。 |
|
| 英文名 |
Astronomy and Meteology |
| 科目所属 |
全学 |
| |
|